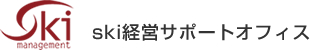ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2021.10.25
- 外国人雇用に関するブログ―――――特定技能「介護」の技能試験の具体例
- 2021.10.20
- 外国人雇用に関するブロブ―――――特定技能「介護」について
- 2021.10.07
- 外国人雇用に関するブログ―――――就労ビザについて「技術・人文知識・国際業務」
外国人雇用に関するブログ―――――特定技能「介護」の技能試験の具体例
前回のブログで在留資格「特定技能」、中でも特に「介護」分野の増加が著しいというお話をしました。
(→詳しくは前回のブログ参照)
2020年9月時点で939人 → 2021年6月時点で2703人と、10か月で3倍近くの増加です。
特定技能の在留資格を得るためには、
「特定技能試験(技能・日本語の2種類)」の合格、
もしくは、「技能実習を有効に終了」した後に移行するか、です。
また、介護分野に限っては、「介護福祉士養成施設を修了した方」「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了の方」も、技能試験・日本語試験が免除になります。
介護分野では、実際は大半が試験合格組であり、合格率は技能試験、日本語試験ともに約80%前後です。(2021年8月の試験結果)
「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格することが必須です
前回のブログでは、日本語テストの具体例についてご紹介したので
今回は、この技能試験の具体的な内容をご紹介します。
<試験の具体的内容>
「技能試験」
母国語にて、行われます。
コンピュータで行い、試験終了後に結果が表示される。
問題の総得点の60%以上で合格となります。結果は5日程度でウェブサイト上にて取得可能。
受験資格は、17歳以上。(インドネシア国籍の方は18歳以上)
受験料は1000円。
技能試験の水準 : 第2号技能実習修了と同等
※介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護
を自ら一定程度実践できるレベル
実施回数:毎月行われます
実施場所:日本国内、海外 詳しくは下記
日本国内・・・全国47都道府県にて。
※例)2021年10月の兵庫県は、神戸三宮4か所、姫路1か所、豊岡1か所にて合計26日程で行われます
海外・・・カンボジア、インドネシア、モンゴル、ネパール、フィリピン、タイ
技能試験内容 : 試験時間 60 分、問題数 45 問
(学科試験:40 問)
・介護の基本(10 問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20 問)
(実技試験:5問)
・生活支援技術(5問)
※写真等の提示で、正しい介護の手順等についての判別、判断を行わせる試験
問題例・・・※実際のテストでは、母国語に翻訳された問題を選択可能
(介護の基本)より
例題1 自己決定を支援する上で把握すべき内容として、
適切なものを1つ選びなさい。
1 家族の意向
2 介護を必要とする人の希望
3 医師の判断
4 経済状況
正答:2
(こころとからだのしくみ)より
例題2 老化にともなう高齢者のからだの変化に関して、
正しいものを1つ選びなさい。
1 個人差は少ない。
2 低い音は、聞こえにくくなる。
3 暑さ寒さを、感じやすくなる。
4 視野が狭くなる。
正答:4
(生活支援技術)より
例題6 右片麻痺があり、杖を使っている人の移動の
基本的な介護として、適切なものを一つ選びなさい。
1 介護者は右前方に立つ。
2 介護者は右後方に立つ。
3 介護者は左前方に立つ。
4 介護者は左後方に立つ。
正答:2
このように、現場にて必要となる介護の知識がテストで問われます。
各外国語での、学習用テキストや、介護福祉専門用語集(※)は、厚生労働省のホームページ上にて無料で公開されています。
(※)例:居宅サービス=in-home service 在宅介護=in-home care
受験者は、これらを利用して母国語にて、介護の勉強をすることができます。
事前に介護や福祉についての知識を得ることができるのは、雇用側、労働者側ともにメリットがありますね。
弊社では、特定技能を含め、外国人雇用、労務管理についての無料相談を行っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
外国人雇用に関するブロブ―――――特定技能「介護」について
昨年からのコロナ禍においても、日本国内の外国人労働者は過去最高人数を記録した、と前回のブログでもお話しました。
人手不足が続く業界では、外国人労働者の活用が積極的に行われています。
日本国内の労働力不足を補うために創設された在留資格「特定技能」(→以前のブログ参照)においては、特に「介護」「飲食料品製造業」分野の増加が著しいです。
具体的な人数を見てみますと、
「介護」
2020年9月時点で939人 → 2021年6月時点で2703人
「飲食料品製造業」
2020年9月時点で5764人 → 2021年6月時点で10450人
となっています。
「介護」分野は、わずか10か月で3倍近くの人数となっています。
今回は、この「特定技能・介護」について、お話しします。
上記の増加率からもわかるように、14分野ある特定技能の中でも「介護」は、外国人労働者に人気のある分野となっています。
特定技能の在留資格を得るためには、
「特定技能試験(技能・日本語の2種類)」の合格、
もしくは、「技能実習を有効に終了」した後に移行するか、
のどちらかとなっています。
介護の分野では、大半が試験合格組です。
介護の試験は、比較的に容易だといわれています。
2021年8月の試験の合格率は、技能試験、日本語試験ともに約80%前後となっています。
さらに、他の分野と違う点は、3年経過後に日本の国家資格「介護福祉士」資格の試験に挑戦することができ、合格すれば在留資格「介護」に変更することができるところです。
在留資格「介護」になれば、在留期間の制限もなく、家族(配偶者・子)の呼び寄せも可能となります
労働者側も、家族と日本で暮らすことができて、雇用側も長期雇用が可能となるWIN WINにつながりやすいのです。
では、具体的に試験の内容をみてみましょう。
<試験の具体的内容>
「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格することが必須です
現在試験を受けられる場所は、①日本国内、②フィリピン、③ネパール、④モンゴル、⑤タイ、です。
「技能試験」
技能試験の水準 : 第2号技能実習修了と同等
※介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護
を自ら一定程度実践できるレベル
実施回数:毎月1回
技能試験内容 : 試験時間 60 分、問題数 45 問 母国語、コンピュータ画面上で解答
(学科試験:40 問)
・介護の基本(10 問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20 問)
(実技試験:5問)
・生活支援技術(5問)
※写真等の提示で、正しい介護の手順等についての判別、判断を行わせる試験
「日本語試験」
ほかの特定技能分野と同じく「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験(JLPT)」N4以上、もしくは介護分野独自の「介護日本語評価試験」の合格
実施回数:年2回(7月と12月)
介護日本語評価試験の内容 : 試験時間 30 分 問題数 15 問
・介護のことば(5問)、介護の会話・声かけ(5問)、介護の文書(5問)
水準 : N4相当・・・ゆっくりと話せば日常会話が理解できる
問題例)漢字の読み書き
___のことばは ひらがなで どう かきますか。1・2・3・4から いちばん
いいものを ひとつ えらんで ください。
あには バスで 会社に 通って います。
1.むかって 2.かよって 3.わたって 4.もどって
介護日本語評価試験・・・実際に介護の現場で使用する言葉など
問題例)Which word has the same meaning as _____? Choose the best answer from 1 to 4.
___の ことばと だいたい おなじ いみのものは どれですか。
いちばん いいものを 1・2・3・4から ひとつ えらんで ください。
加藤(かとう)さんは、車椅子(くるまいす)を使(つか)っています。
1 食(た)べるために使(つか)う道具(どうぐ)
2 移動(いどう)するために使(つか)う道具(どうぐ)
3 入浴(にゅうよく)するために使(つか)う道具(どうぐ)
4 音(おと)を聞(き)くために使(つか)う道具(どうぐ)
これらの試験に合格した場合の「結果通知書」は、受験日から10年後まで有効となります。
基本的な日本語知識と、介護の勉強をした人材ですので、即戦力として、雇用側にもメリットがある制度です。
特定技能「介護」では、訪問サービスは行うことができません。
しかし、身体的業務など他の業務は行うことができるため、制限が少なく、幅広い範囲の業務に携わることが可能です。
弊社では、無料相談を行っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
外国人雇用に関するブログ―――――就労ビザについて「技術・人文知識・国際業務」
外国籍の方が日本で就労するための在留資格はいくつかありますが、最も一般的で幅広く使用されている就労ビザといえば「技術・人文知識・国際業務」です。
具体的に、該当する職種は以下の通りになります。
技術・・・理系分野。機械工学、電気工学、情報工学などに関連する業務
例)IT関連、システムエンジニア、機械工学等の技術者
人文知識・・・文系分野。経営学、商学などに関連する業務
例)マーケティング業務、営業
国際業務・・・翻訳・通訳など語学の指導、広報、宣伝、または海外取引業務
例)民間語学学校の英語講師(公立学校の英語教師は非該当)
就労ビザの取得要件としては、
① 大学卒業(母国の大学でも可)以上か、日本の専門学校卒業の学歴(母国での専門学校卒業は不可)
もしくは
② 10年以上の職務経験
となっております。
① の場合、大学や専門学校で専攻した勉強の内容と、日本での職務内容が一致することが重要です。
もしくは、母国の文化や言語を業務に使用するとして「国際業務」で申請するか、です。
② の場合も、同じく、職務経験の内容と日本での職務内容が一致していることが重要です。
① ②ともに、申請時に証明することが必要です。(卒業証書、在籍証明書、等)
また、例外的に「国際業務」に「3年以上の実務経験」がある場合は、在留資格を取得できる場合があります。
以下は、先日当社に実際に、お問い合わせがあった件です。
・母国で文系の大学を卒業した外国人の方(経営学部)
・日本語検定N2保持で、日本語日常会話は問題なし
・日本の工場で製造やライン作業に従事する仕事に内定が出たので、就労ビザに変更したい
雇用企業さまで、初めての外国人労働者採用であったらしく、弊社にビザのサポートのご相談をいただきました。
しかし、この場合は、基本的には就労ビザはおりません。
なぜなら、大学で勉強した経営の勉強と、工場の製造ラインでの業種が一致しないからです。
勤務先が工場であっても、例えば、他の外国人労働者(技能実習生など)を統括する立場であったり、もしくは、海外の会社と取引を行っており、そのための翻訳・通訳としての仕事に従事する場合であった場合、などは上記の条件の大卒外国人の方に就労ビザが下りる可能性は高くなります。
もちろん、就労ビザの要件①で述べたように、上記の大卒外国人が、勤務先工場の製造業務に関する分野の勉強を大学でしていた場合は、就労ビザは取得可能(ほかの条件も満たしていれば)かと思われます。
また、事業計画書を作成し、最初の半年間のみ現場仕事を学び、その後は管理職に就く、などという場合は許可される可能性があります。
今回は、外国人が一人の職場であり、外国人の母国との取引等もなく通訳としての採用でもなく、単純労働に従事する見込みのため、上記ケースにも該当しません。
企業側がすでに内定を出しており、雇用側・労働者側、双方のニーズはマッチしていたと思われるのですが、在留資格変更(この場合は学生ビザ→就労ビザ)の許可が下りなければ、働くことはできません。
要件を満たさない限り、許可されませんので、その旨をお伝えさせていただきました。
コロナ禍においても、国内での外国人労働者は過去最高の人数を記録し、今後ますますの増加が考えられます。
外国人雇用、労務管理に関しては、さまざまな制約や規則があります。
弊社では、無料相談を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。